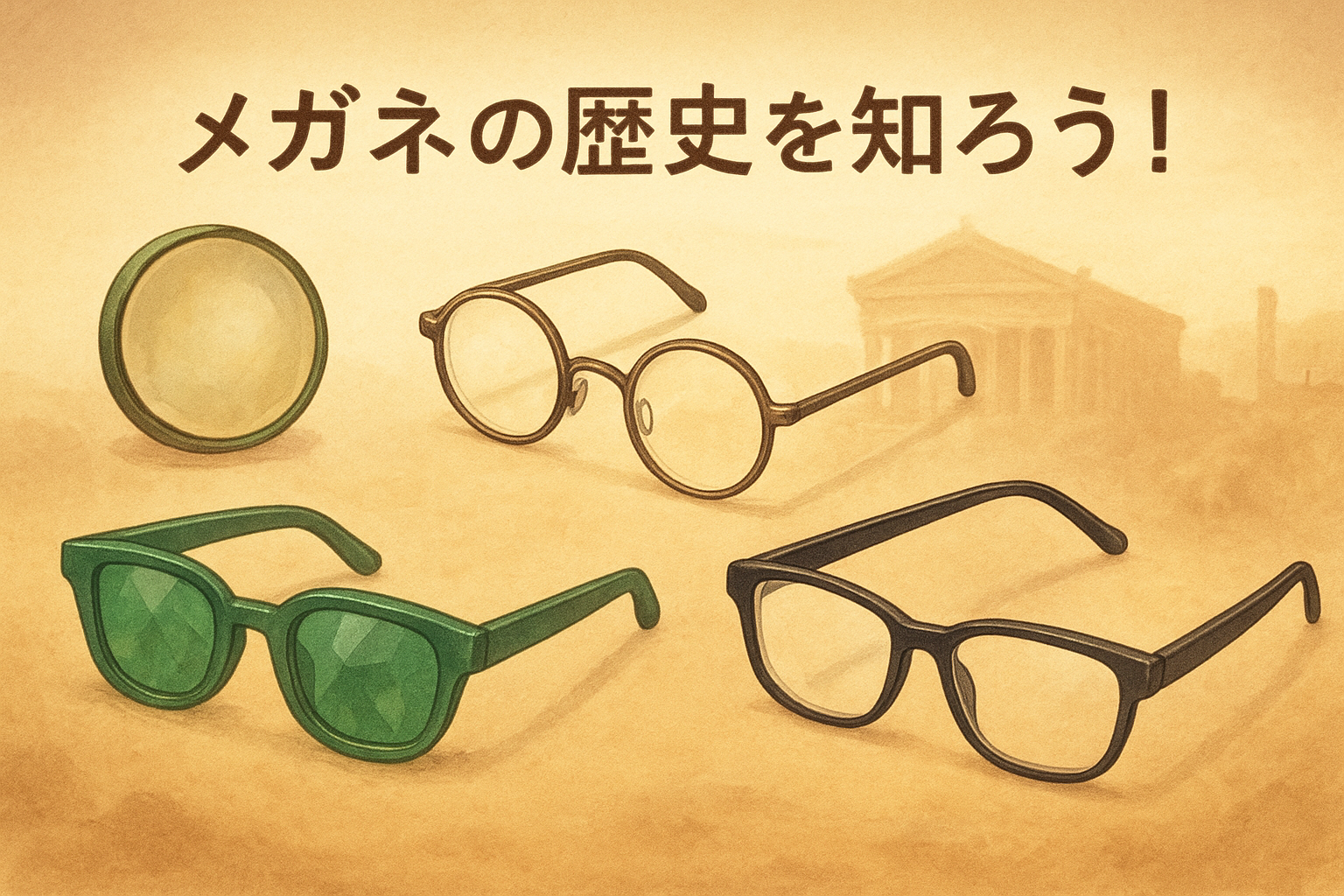
こんにちは奈良天理駅前メガネのスズキです。
少しずつ暑さが落ち着き、読書の秋が近づいてきましたね。
さて、読書にメガネが手放せない方も多いと思いますが
そのメガネがどのような歴史を辿ってきたかご存じでしょうか。
視力を補正したり、紫外線から目を守ったり、ファッションアイテムとして活躍したりと、その役割はさまざまです。
では、このメガネは一体いつから人類の歴史に登場したのでしょうか?
古代:レンズのはじまり
人類はかなり早い時期から「透明な石やガラスがものを拡大する」ことに気づいていました。
- 古代エジプト
ヒエログリフの中には、レンズや拡大を表すとされる絵文字があり、当時から光学的な道具が使われていた可能性が指摘されています。 - 紀元前1世紀
ローマの皇帝ネロは、剣闘士の試合を観戦する際に エメラルドを磨いた石をサングラス代わり に用いたと伝わります。これは光を遮るための利用で、視力矯正というよりは「眩しさ除け」に近いものでした。
中世:視力を補う道具の誕生
「視力を矯正するためのメガネ」に近い形が現れるのは中世です。
- 9世紀頃
アラビアの学者たちが光学の研究を進め、レンズを通した拡大や矯正の知識が広まりました。これが「メガネの起源」につながる重要な一歩となります。 - 13世紀 イタリア
現在の「メガネ」に近い形が登場。フィレンツェの修道士や学者が本を読むために、凸レンズを使った眼鏡を愛用していた記録が残っています。
この頃は耳にかけるつるはなく、鼻に挟んで使う「鼻眼鏡(ピンチネズ)」のような形式でした。
日本への伝来
メガネが日本にやってきたのは16世紀。
- 1549年、フランシスコ・ザビエル来日
ザビエルが布教の際に使用していた眼鏡が、日本人が初めて見たメガネだといわれています。
当時は珍しい「西洋の不思議な道具」として、メガネは権威の象徴でもありました。 - 江戸時代
長崎を通じて輸入されるようになり、オランダ製のメガネが武士や僧侶に愛用されました。まだ高級品で、一般庶民が使うものではありませんでした。
国産メガネの誕生
- 明治時代
近代化とともに、国内でもメガネの製造が始まりました。
特に 福井県鯖江市 は昭和以降、眼鏡フレームの一大産地となり、現在も「世界三大眼鏡産地」として知られています。
現代のメガネ
今では、視力矯正だけでなく、ブルーライトカット、スポーツ用、防護用、さらにはファッションアイテムとして幅広く活躍。
古代エジプトのレンズから数千年、人類は「よく見たい」「目を守りたい」という願いを形にしてきました。
おわりに
メガネの歴史を振り返ると、単なる道具以上に「知識や文化を広める力」を持っていたことが分かります。
もしメガネがなければ、多くの学者や芸術家はその業績を残せなかったかもしれません。
そう考えると、日常の中で何気なくかけているメガネが、実はとても偉大な発明だと感じられますね。
そして、日常で私たちがかけるメガネも、目の健康や生活の質を支える大切なパートナーです。
奈良・天理駅前の メガネのスズキ では、視力矯正はもちろん、ブルーライトカットやおしゃれなフレームまで幅広くご用意しています。
初めての方も、買い替えをご検討の方も、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
あなたの目にぴったりの一本を、一緒に見つけましょう。